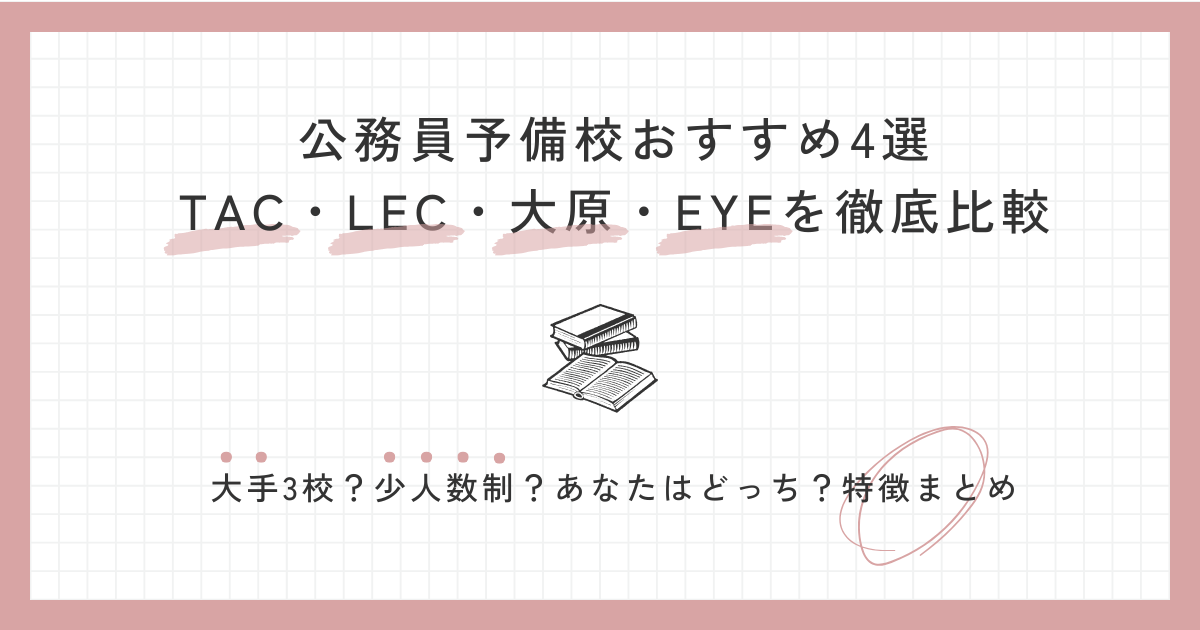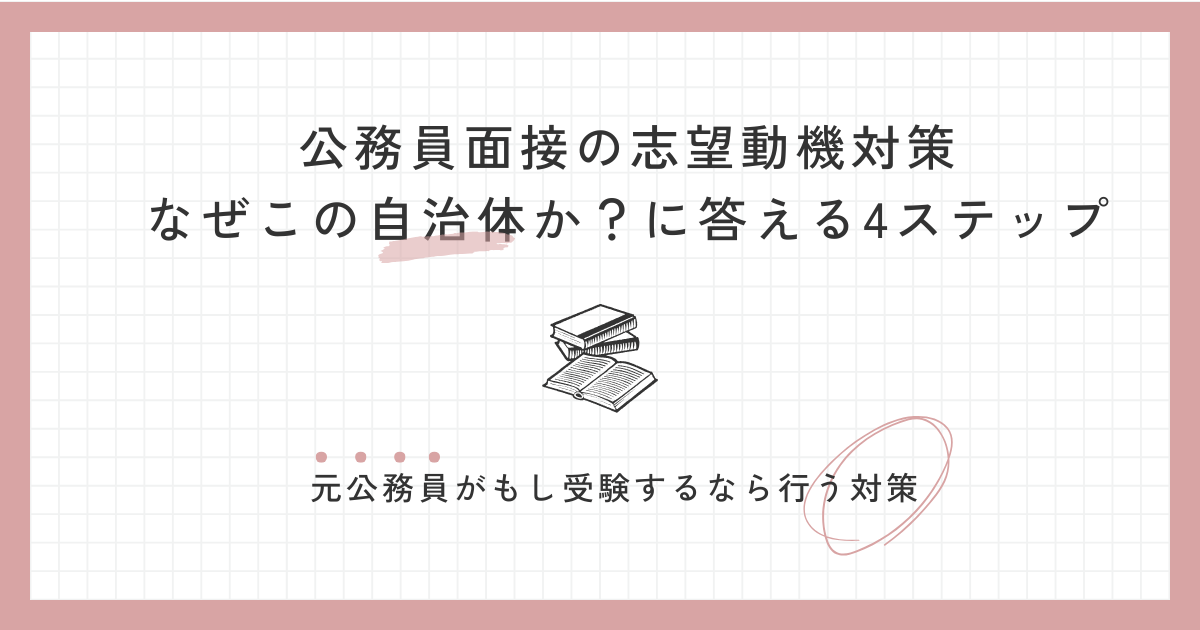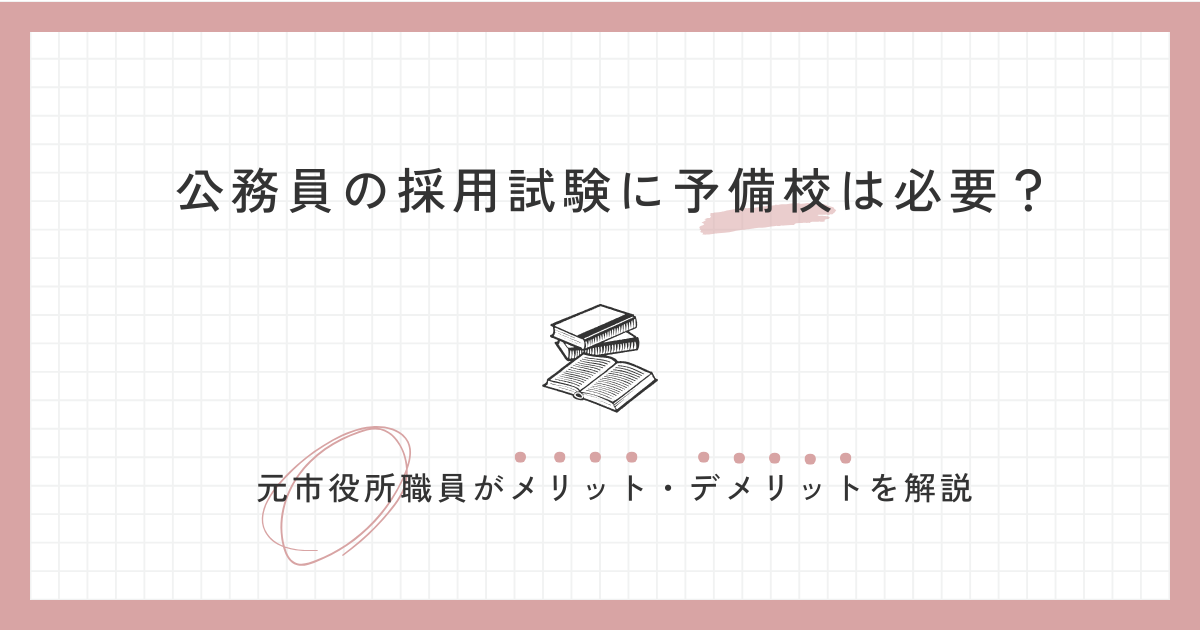【保存版】これが公務員への道!採用試験の種類・併願のコツ・合格までの流れを元市役所職員が解説
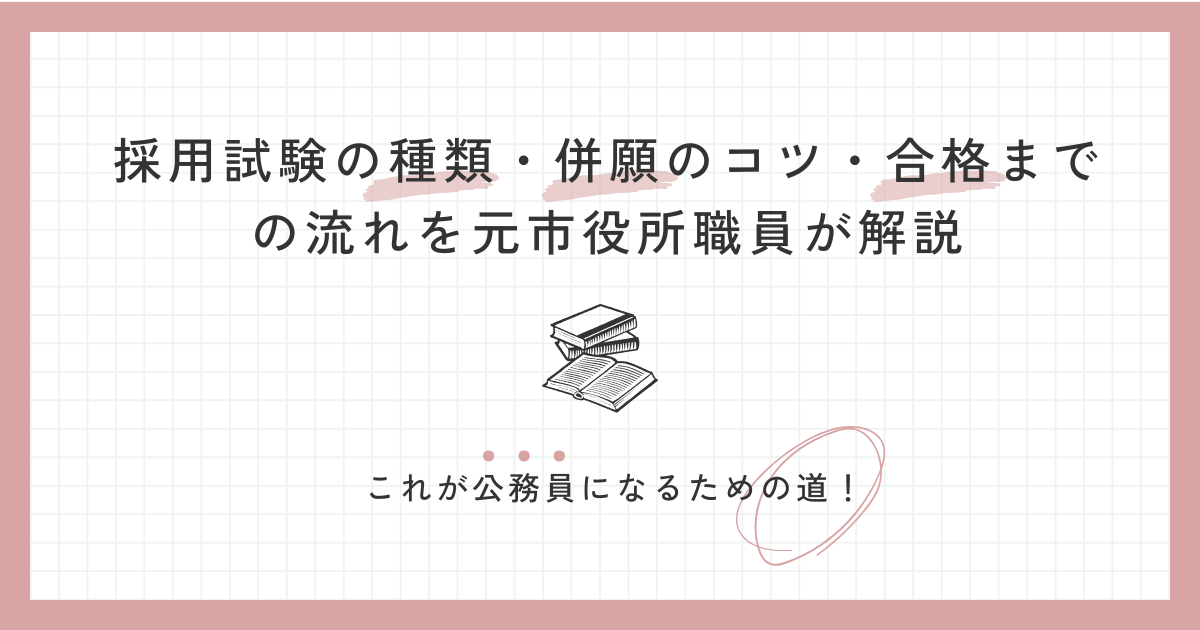
「そうだ!公務員に転職しよう」と思ったとき、まず最初にぶつかる壁。
それが、
「公務員ってどうやったらなれるのか?」
という問題です。
公務員の採用試験に合格する必要があるのは知っているけど…試験内容って?併願できるの?と疑問を持たれる人も多いのではないでしょうか。
今回は、これから公務員を目指す方に向けて、試験の種類とその違いを、元市役所職員のぴょん吉がシンプルにわかりやすく解説します。
実際に私が受けた試験は、国家一般職と地方上級(一般行政職)です。
多種多様な公務員
一口に「公務員」と言っても、その種類はさまざま。大きく分けると、以下のような分類があります。
- 国家公務員(総合職・一般職など)
- 地方公務員(都道府県・市区町村)
- 特別職公務員(警察官・消防官・自衛官など)
国家公務員の種類
国家公務員は、国の省庁や出先機関(税務署や労働基準監督署など)で働く人たちです。
◆ 総合職(旧・国家Ⅰ種)
エリート中のエリート。いわゆるキャリア組。政策立案や管理職を目指す人向け。
出世が早く、将来は局長・次官などの幹部候補としてキャリアを積む。
◆ 一般職(旧・国家Ⅱ種)
いわゆるノンキャリア。総合職の企画立案を支える事務職員。
幹部になることも可能だが、昇進スピードは総合職より緩やか。
◆ 専門職
特定の分野に特化した職種。代表例は以下:
- 国税専門官(税務署で働く)
- 労働基準監督官(労働基準監督署)
- 裁判所職員
- 法務省専門職員(人間科学など)
地方公務員の種類
一方、地方公務員は都道府県・市区町村で働く人たち。以下のように分かれます。
◆ 一般行政職(事務職)
市役所や県庁などで働く、もっともスタンダードな職種。
「行政職」と書かれているのがこのタイプで、窓口業務・企画・福祉・税務など部署はさまざま。
◆ 技術職(土木・建築・電気など)
インフラ整備や建築管理など土木関係の部署に配属されがち。専門性が求められる技術系公務員。
◆ 資格職・専門職
保育士、栄養士、看護師、社会福祉士、司書など、資格が必要な職種。
保育士で保育園など資格に応じた部署に配属される。
それぞれの公務員採用試験
国家一般職と一般行政職との試験日は異なるため、併願可能です。
地元の市役所一本に絞るとかは非常にリスキーです。試験範囲はほぼ同じなので併願がおすすめ!
国家公務員(国家一般職)
国家一般職の試験は、以下の流れで行われます。
- 筆記試験(教養試験・専門職試験)
- 人事院面接
- 官庁訪問
❶ 筆記試験
筆記試験は、教養試験と専門試験が行われます。
教養試験は、数的処理・文章理解・社会科学などの問題が出題されます。
就活で民間企業を受けていれば、イメージがつくと思いますが、内容としてはSPIに近いです。ただ出題範囲は広く、SPIにない物理、生物、日本史や世界史などが出ます。
専門試験は、その名の通り法律・経済・行政法などの専門的知識が問われます。
就活で民間企業しか受けていない人は勉強必須。
❷ 人事院面接
人事院の職員による面接が行われます。内容は一般的な内容で、公務員の適正があるかどうかがチェックされてます。
この面接に合格すると、採用候補者名簿に掲載されることになり、ようやく自分の行きたい省庁の採用面接を受けることができます。
※ この面接に合格しても国家公務員になれるわけではないので注意
❸ 官庁訪問
官庁訪問は、志望省庁へ実際に出向き業務説明や面接を受けるものです。これに合格すれば晴れて国家公務員になれます。
内容や面接回数は省庁ごとに異なっており、完全にブラックボックスです。
私が受けた省庁は、1日で3回の面接を行いました。
1回受けるごとに、エレベーターか別室に案内されます。エレベーターであれば不採用、別室であれば次の選考という非常にスリリングな採用試験でした。1回目、2回目ともに面接後すぐに結果がわかります。
最終面接だけは別で、その日の夜0時過ぎくらいに省庁から電話で採用の連絡がありました。
遅すぎだろ!って思いますが、そんな感じなので官庁訪問当日は最終までいったら寝ないようにしましょう。
地方公務員(一般行政職)
続いて、県庁や市役所の職員になるための採用試験ですが、国家一般職の試験とは若干異なります。
- 筆記試験(教養試験・専門職試験・小論文)
- 面接
県庁や政令市といった大きな自治体は、試験日は同日に行われますが、他の市町村とは別日になるので、可能な限り併願するのがベスト。
❶ 筆記試験
筆記試験は、教養試験と専門試験に加えて小論文が加わります。
小論文は、少子高齢化などの社会問題が題材に取り上げることが多いです。国家一般職だけではなく、一般行政職を受けるのであれば、小論文の対策が必要です。
❷ 面接
面接の内容や回数については、各自治体によって異なります。
私が受けた自治体は、面接を3回行いました。最終面接を突破すると晴れて地方自治体の職員になれます。
1回目が集団面接、2回目がグループワーク、3回目が個別面接でした。
選考通過の連絡は、官庁訪問とは異なり、日にちをあけてホームページや、紙の通知が届きます。
官庁訪問を経験すると、この結果発表までが非常に焦ったい。
まとめ
公務員には、**国家公務員(総合職・一般職・専門職)と地方公務員(都道府県・市区町村)**があり、それぞれ試験の内容・流れが異なります。
**国家一般職は「筆記→人事院面接→官庁訪問」**の3ステップ。特に官庁訪問は省庁ごとに内容が異なり、緊張感のある選考が行われます。
地方上級(一般行政職)は「筆記(+小論文)→複数回の面接」。論文や面接の内容は自治体ごとに異なり、自治体ごとに特性があります。
いずれの試験も教養試験+専門試験が基本。SPIに似た教養に加え、法律・経済などの専門科目が問われるため、しっかりとした準備が必要です。
国家一般と地方上級は試験日が異なるため、併願可能。地元の市役所一本に絞るのはリスクが高いため、複数受験が現実的。
公務員試験は「種類が多くて複雑」に見えますが、仕組みを理解すれば戦略的に受験できます。
この記事をきっかけに、自分に合った受験スタイルや併願先を見つけ、早めに対策を始めていきましょう!